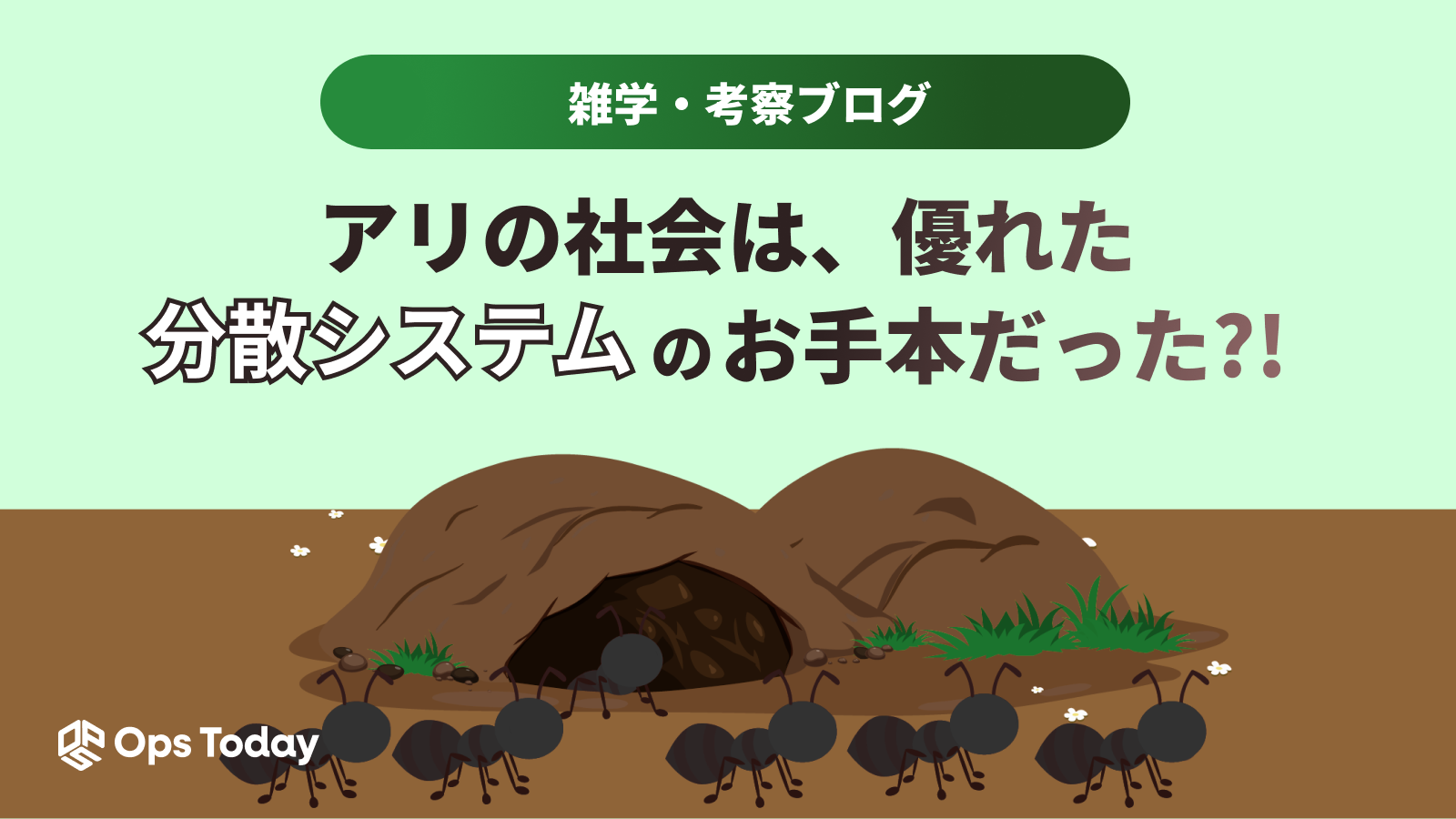
アリの社会は、優れた「分散システム」のお手本だった?!
最近、娘に空前のアリさんブームが到来。
毎日飽きもせずにアリを探しては、動きをじーっと観察しています。早く帰りたい気持ちをグッとこらえ、アリの観察に付き合う日々。

先日、図書館でアリの生態を調べてみたところ、「あれ、これって我々の仕事でいう、優れた『分散システム』そのものじゃないか?」と、思わぬ発見をしてしまいました。
今日は、そんな身近なアリの社会から見えてきた、クラウド時代のシステム運用に役立つかもしれないヒントについて、少しお話ししてみたいと思います!
アリ社会に上司はいない!リーダー不在のスーパーチーム
アリの社会には女王アリがいますが、実は彼女、みんなに指示を出す司令塔(リーダー)というわけではありません。女王アリの主な役割は繁殖で、個々の働きアリたちは、誰かの命令を待つことなく、それぞれが自律的に動いています。
では、どうやって連携しているのか…?
その理由は、フェロモンという化学物質でのシンプルな情報伝達や、周りの状況に応じたごく簡単なルールに従っているだけ。それなのに、巣作り、食料探し、外敵からの防衛といった高度なタスクを、チーム全体として見事にこなしています。
これは「創発」と呼ばれる現象で、個々の単純な行動が、全体として予測もつかないような高度で複雑な秩序を生み出す、というものです。中央の司令塔がなくても、個々が自律的に動くことで、しなやかで強い社会システムが出来上がっているんですね!
クラウドも同じ思想?自律的な分散システムのすごいところ
調べてみると、この「リーダーなき組織」という考え方は、私たちが普段触れているクラウドのアーキテクチャ、特に分散システムやマイクロサービスの思想と、驚くほどよく似ています!
昔ながらの一枚岩のシステムだと、一つの機能がダメになっただけで、システム全体が停止してしまうリスクがありました。しかし、機能を小さなサービスの集まりに分けて、それぞれが独立して動く分散システムなら、一部でトラブルが起きても他への影響を最小限にできます。
これは、アリの社会で一部の個体がいなくなっても社会全体は問題なく機能し続ける「耐障害性」と、まったく同じ考え方です。
スケーラビリティまで体現…?!
また、クラウドの大きなメリット「スケーラビリティ」も、彼らの社会から学べます。スケーラビリティとは、仕事の量に合わせて、システムの処理能力を柔軟に増やしたり減らしたりできる能力のことですよね。
例えば、大量のエサが見つかると、多くのアリがそこに集まってきて一気に巣へ運びます。仕事の量に応じて、働き手の数が自然に調整されるわけです。
これとそっくりなことを、クラウドサービスは自動でやってくれます。
| クラウドサービスの例 | 機能 |
|---|---|
| AWS Auto Scaling | EC2インスタンス(仮想サーバー)の数を、トラフィックなどの条件に応じて自動で増やしたり減らしたりします。 |
| Azure Virtual Machine Scale Sets | こちらも同様に、需要に応じて仮想マシンの数を自動でスケールさせることができます。 |
| Google Cloud Managed Instance Groups | 負荷に応じてインスタンスの数を自動調整し、パフォーマンスを保ちます。 |
これらの機能は、まさにアリの社会のように、私たちシステム管理者が常に監視していなくても、システム自体が自律的に状況を判断し、最適な状態を保ってくれる仕組みなんです。
運用現場の我々が、自然界に学ぶ「しなやかさ」
日々の運用業務では、予期せぬアクセスの急増や、突然のハードウェア障害など、ヒヤッとすることがつきものです。そのたびにアラートに叩き起こされ、対応に追われる…なんて経験は、多くのエンジニアにとって「あるある!」と頷きたくなるものです。
しかし、アリの社会が教えてくれるのは、一つ一つの部品が自律的に動くことで、システム全体が変化に強く、しなやかになるという事実です。
一部のサーバーがダウンしても、残りが自動で処理を引き継ぐ。アクセスが増えたら、システムが自動でサーバーを増やす。そんな自律的な仕組みを上手に作っていくことで、私たちはもっと安心して夜を過ごせるようになります。
まとめ
自然界が何億年もかけて作り上げた、この見事な分散システム。
次にコーヒーブレイクで一息つくとき、窓の外の小さな生き物たちの働き方に、未来のシステムのヒントを探してみてはいかがでしょうか。面白いビジネスアイディアや、クスッと笑える同僚との雑談ネタなど、そこから何かが見つかるかもしれませんね。



