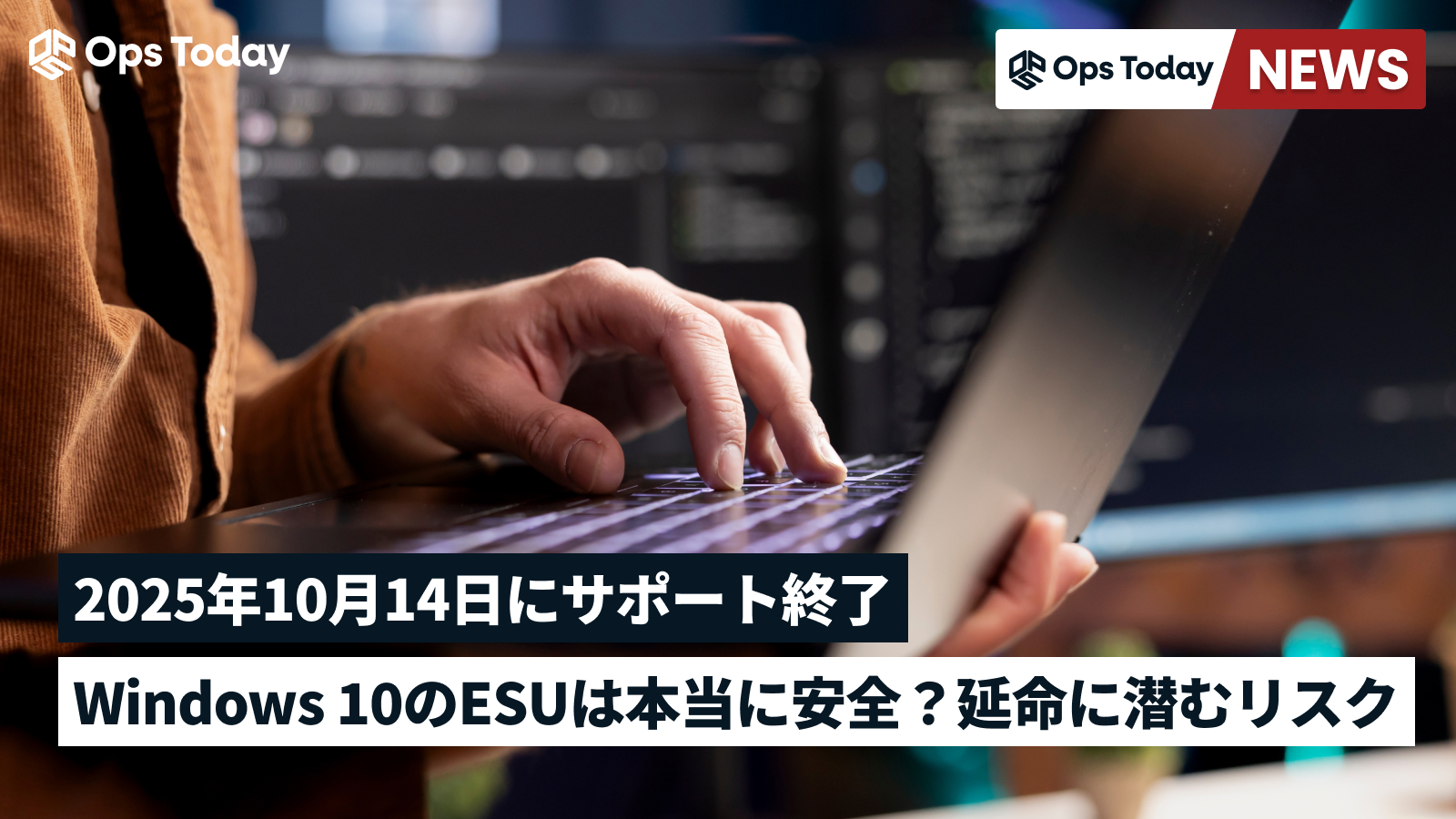
【サポート終了】 Windows 10のESUは本当に安全?延命に潜む多数のリスク
本日2025年10月14日で、Windows 10のサポートが終了となります。
これを前にマイクロソフトは、延長セキュリティ更新(ESU)の有料提供、さらに一部個人ユーザーには1年間無料という選択肢を提示した。この発表を受け、Windows 11への移行をひとまず見送り、使い慣れた環境を維持する「延命」の道を選んだ方もいるだろう。
しかし、その決断の裏に潜むデメリットや、依然として残る深刻なセキュリティリスクを、果たして正しく理解しているだろうか。本稿は、有料・無料を問わずESUによる延命を選択した人々へ向け、今改めて直視すべき課題を、システム運用の専門家の視点から解説する。
ESUの条件とコスト
まず、延長セキュリティ更新(ESU)の仕組みを正確に理解する必要がある。これは、サポート終了後も最長3年間、セキュリティ更新のみを受け取れる有料の年間サブスクリプションだ。
提供されるのは「重大(Critical)」および「重要(Important)」と評価された脆弱性への対応のみで、新機能の追加や性能改善は一切行われない。
個人ユーザーが無料で利用する条件
話題の「無料ESU」は、以下のいずれかの条件を満たす個人ユーザーが対象となる。
| 無料でESUを利用するための条件 | 注意点 |
|---|---|
| Windowsバックアップで設定をクラウドに同期 | Microsoftアカウントが必須。OneDriveの無料容量(5GB)を超えるバックアップには追加料金が必要になる場合がある。 |
| Microsoft Rewardsのポイントを1,000ポイント利用 | 日常的にBing検索などマイクロソフト製サービスを利用していないユーザーにはハードルが高い。 |
これらの条件を満たせない場合、個人ユーザーは30ドルを支払うことで1年間のESUに登録できる。いずれにせよ、対象となるのは、Windows 10のバージョン「22H2」を実行しているPCのみである点に注意が必要だ。
有料プランの価格体系
一方で、法人ユーザーや、2年目以降も延長を望む場合の価格は年々倍増していく設定となっている。
| 対象ユーザー | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
|---|---|---|---|
| 法人 | $61 | $122 | $244 |
| 個人 | $30 | 提供なし (現時点) | 提供なし (現時点) |
この価格設定は、ESUが決して恒久的な解決策ではなく、あくまでWindows 11への移行を促すための一時的な猶予期間であると物語っているようにも見える。
ESUでは解決しない「延命」のデメリット4点
たとえ無料ESUを適用できたとしても、古いOSを使い続けること自体のデメリットは解消されない。
最も深刻な脅威、セキュリティリスクの増加
最も強調したいのが、ESUがセキュリティの万能薬ではないという厳然たる事実だ。ESUがカバーするのは、マイクロソフトが「重大」「重要」と判断した一部の脆弱性のみ。それ以外の無数の脆弱性は放置されるため、攻撃者にとって格好の侵入口となる危険を孕んでいる。
さらに見落とされがちだが、Windows 10標準搭載のウイルス対策ソフト「Microsoft Defender」も、OS本体と同時にサポートが終了し、定義ファイルの更新が停止する可能性が高い。これは、城門の警備兵が不在になるに等しい。
たとえサードパーティ製のセキュリティソフトを導入しても、OSという土台そのものに脆弱性が残っていては、ランサムウェア攻撃や情報漏洩といった致命的なインシデントを防ぎきることは困難を極める。
システムの陳腐化と不安定化
ESUが提供するのは、あくまでセキュリティ関連の修正のみだ。パフォーマンスの低下を引き起こすバグや、特定の操作で発生するフリーズといった、セキュリティ以外の不具合は一切修正されない。
つまり、OSは時間と共に劣化していく一方であり、システムの安定性は低下し続ける。
原因不明のクラッシュによる業務中断やデータ損失のリスクは、ESUを適用しても何ら変わらない。これは、致命傷を避けるための応急処置は施すが、体力の低下や持病の悪化は放置するようなものだ。
互換性の喪失で、さまざまなアプリが利用不可の可能性
OSの進化が止まるということは、周辺のエコシステムからも取り残されることを意味する。ソフトウェア開発者は、サポートが終了したOSを動作保証対象から次々と外していく。
これは、日常業務で利用する会計ソフトやCAD、デザインツールといった専門的なアプリケーションが、ある日突然アップデートできなくなったり、新規導入が不可能になったりするリスクに直結する。
同様に、新しく導入するプリンターやスキャナー、Webカメラといったハードウェアも、古いOS用のドライバーが提供されず、利用できない事態が想定される。結果として、組織全体の生産性や競争力が、OSという足枷によって徐々に蝕まれていく可能性がある。
新旧OS混在が招く、管理コストの増大
組織内にWindows 10とWindows 11が混在する場合、情報システム部門の管理コストを確実に増大させる。
それぞれのOSに対して異なる管理ポリシーやソフトウェア配布の仕組み、トラブルシューティングの手法が必要となり、運用は複雑化する。セキュリティ設定の標準化も困難になり、管理の隙が生まれやすくなる。
結果として、人為的な設定ミスによるセキュリティインシデントのリスクを高めることにも繋がりかねない。ESUのライセンス費用という直接的なコストだけでなく、こうした目に見えない運用コストの増大も、延命がもたらす深刻なデメリットなのである。
今後の対応
ESUによる延命を選択した方も、ESUは「安全の保証書」ではなくあくまで限定的な延命措置であり、リスクをゼロにするものではないことを再認識する必要がある。
ESUで得た時間は、安全な移行を実現するための「準備期間」と捉えると良いだろう。使用中のPCがWindows 11のシステム要件を満たすかを確認し、満たさない場合はPCの買い替え予算の確保など、具体的な計画を今すぐ再始動させることが賢明だ。
また、万が一の事態に備え、定期的な完全バックアップの取得は、もはや義務であると言っても良いだろう。
まとめ
有料・無料の選択肢が示されたことで、Windows 10の延命は一見、合理的な判断に思えるかもしれない。しかし、「まだ使えるから」という理由で延命を続けることは、自らセキュリティリスクを抱え込むことに他ならない。
今一度、その選択が長期的に見て本当に正しいのかを問い直し、より安全で生産性の高い未来への投資として、計画的な移行を検討してみてはいかがだろうか。



