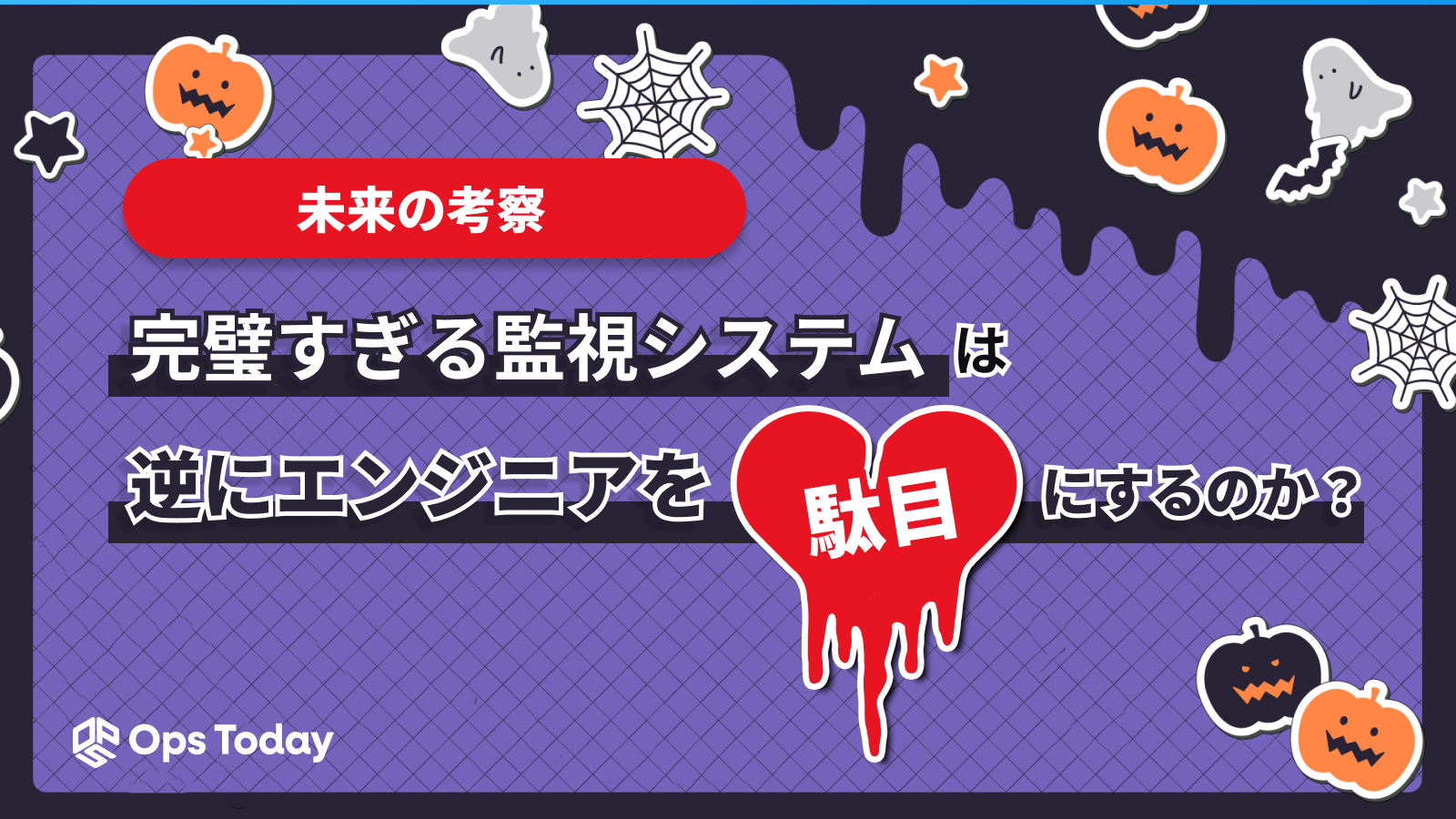
【考察】完璧すぎる監視システムは、逆にエンジニアを「ダメ」にするのか?
システムの安定稼働に、もはや欠かせない存在となった監視システム。近年はAI技術の進化も相まって、その精度は驚くほど向上しています。
しかし、もしアラートが的確すぎたら、エンジニアの成長機会を奪ってしまうかもしれない…。
そんな皮肉な状況はあり得るのか?
自動化時代のエンジニアが「腕を鈍らせない」ためには、どうすれば良いのか?

この記事で、考察してみます。
監視システムの進化と、AIOpsの登場
昔の監視システムといえば、CPU使用率やメモリ使用量なんかの閾値(しきいち)を決めて、それを超えたらアラートを出すのが一般的でした。でも、システムがどんどん複雑になるにつれて、もっと賢い監視が必要になってきました。
そこで現れたのが、皆さんご存じのとおり、AIで異常の予兆をキャッチしたり、原因を分析したりする「AIOps」です。
人間じゃとても追いきれない量のログやメトリクスから、不穏な兆候を見つけ出して、根本原因の特定までサポートしてくれます。まさに、システム運用の「匠の技」をAIが代替してくれる時代の到来と言えるでしょう。
関連記事:AIOpsとは?導入方法と考慮すべきポイントを徹底解説
「完璧な」アラートがもたらす、諸刃の剣
AIOpsによって、障害対応の迅速化や運用負荷の軽減といった大きなメリットがもたらされるのは間違いありません。しかし、その一方で、ある種の「副作用」も考えられます。
それは、エンジニアが自ら障害原因を推測し、試行錯誤しながら解決策を探るという、貴重な学びの機会が失われてしまうのではないか…?という点です。

あまりにも的確なアラートが「正解」を教えてくれる環境に慣れてしまうと、エンジニアはただその指示に従うだけになり、システム全体を俯瞰(ふかん)して問題を捉える力や、未知の障害に立ち向かうための応用力が育ちにくくなるかもしれません。
これは、自動化が進んだ環境で、人間が注意深さを失ってしまう「コンプリセンシー(自己満足、慢心)」と呼ばれる状態にも似ています。
| 完璧すぎる監視がもたらす懸念点 | 具体例 |
|---|---|
| 思考力の低下 | アラートが示す原因以外を疑わなくなる |
| 応用力の欠如 | 未知の障害や複雑な問題への対応力が鈍る |
| スキルアップの停滞 | 障害調査のプロセスを経験する機会が減る |
【事例1】Microsoftとカーネギーメロン大学の共同研究
マイクロソフトとカーネギーメロン大学の共同研究によると、生成AIに過度に依存している従業員は、批判的思考(クリティカルシンキング)が求められる場面で、そうでない従業員よりも苦労する傾向があることが示されました。
AIを信頼し、日常的に思考を委ねていると、いざ自分で考えなければならない状況で能力を発揮しにくくなる、というわけです。
この現象は「認知オフローディング」とも呼ばれています。 認知オフローディングとは、記憶や問題解決といった認知プロセスを、AIなどの外部ツールに委ねてしまうことです。
【事例2】マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボの研究
MITメディアラボの脳波研究は、さらに踏み込んだ結果を示しています。
この研究では、被験者を3つのグループ(①ChatGPTを使う、②Google検索を使う、③自分の頭脳のみ)に分け、小論文を執筆してもらいました。
その際の脳波を測定したところ、ChatGPTを使ったグループは、脳の活動が明らかに低下していることが確認されたのです。 興味深いことに、AIが作成した文章は構成も言語もほぼ完璧でしたが、内容はどれも似通っており、「魂がないように感じた」と評価されています。
これは、思考のプロセスそのものをAIに委ねてしまうことで、独自の思考を深める機会が失われていることを示唆しています。
自動化時代のエンジニアが「腕を鈍らせない」ためには
では、我々エンジニアは、どうすれば高度な監視システムの恩恵を受けつつ、スキルを維持・向上できるでしょうか?
ひとつの案として考えられるのは、監視システムを「ブラックボックス」にしないことです。

…なぜそのアラートが発せられたのか?
…どのようなロジックで異常を検知したのか?
といったシステムの裏側にある仕組みを理解しようとするクセをつけることが重要です。
また、日頃からシステムのアーキテクチャや依存関係を深く理解し、「次はここが危ないかも?」など、潜在的なリスクを予測するトレーニングも有効ではないでしょうか。

問題が起きてから動くより、先回りしてシステムの健康を守る。そんな視点が、我々エンジニアの価値を高めていくはずです。
まとめ
技術の進化にただ乗っかるのではなく、その技術をどうやって賢く使いこなし、自分の成長につなげるか?これは、これからの時代を生きるエンジニアにとって非常に重要なテーマと言えるでしょう。
最後は、筆者から皆さんへのメッセージで締めくくりたいと思います。
「とはいえ、AIOpsは敵ではなく、最高の相棒だ!」

強力なツールと上手く付き合いながら、我々エンジニア自身も一緒に進化していきましょう!



