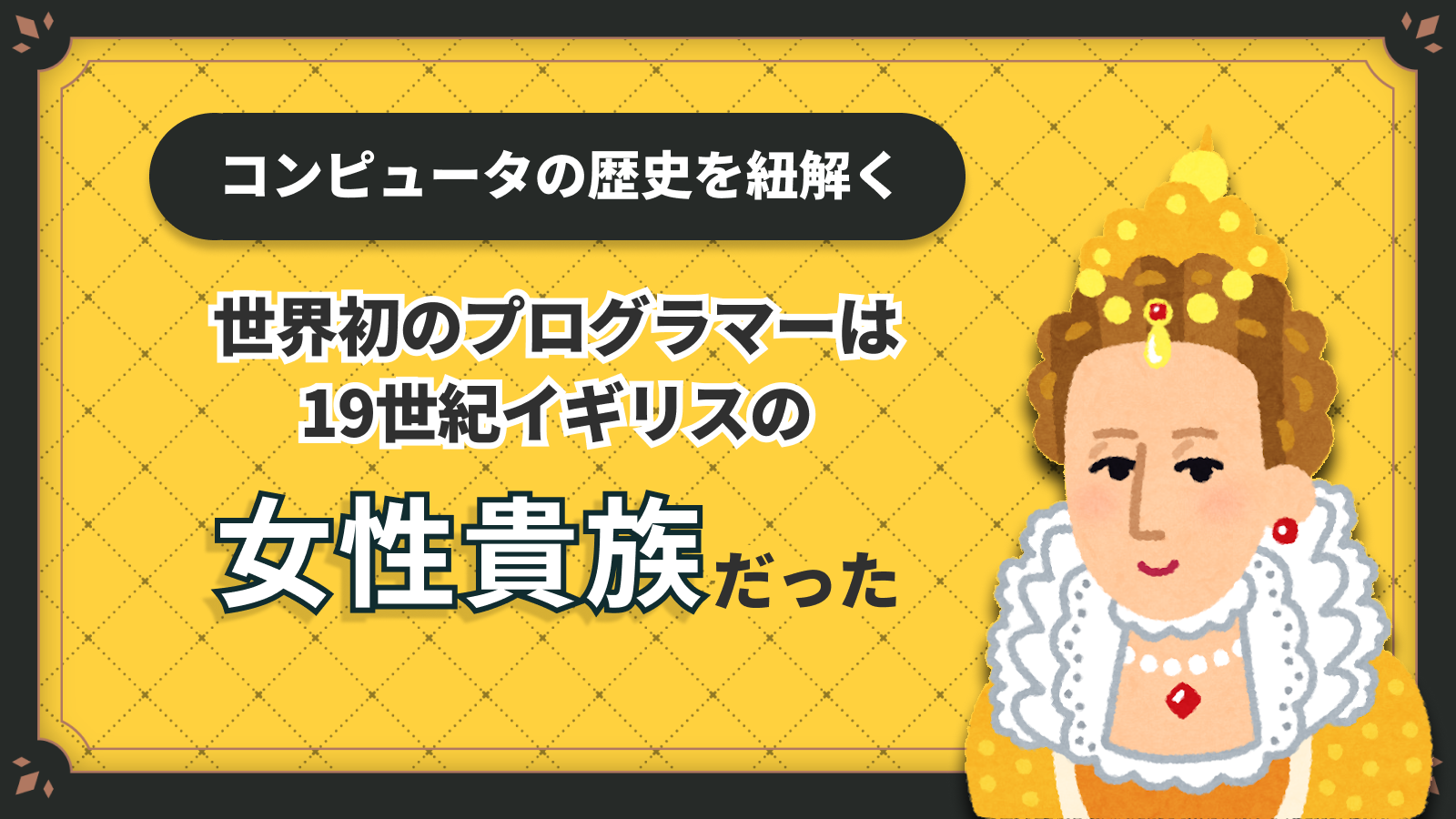
世界初のプログラマーは、19世紀イギリスの女性貴族だった
日々のシステム運用、お疲れ様です。AIや自動化が進化する現代ですが、その根源をたどると、19世紀のイギリスにたどり着きます。
本日のコラムは、そんな時代に「世界初のプログラマー」と呼ばれた女性貴族、エイダ・ラブレスの物語をご紹介します。(画像はイメージです!)

詩人の娘が、まさかの理系女子に?
エイダ・ラブレスが生まれたのは1815年。父親は超有名な詩人のバイロン卿です。 ただ、父親はスキャンダルが多く、エイダが生まれてすぐに出て行ってしまいました。
母親は、娘が父親のような詩人特有の気質にならないように、と願ったのか、幼い頃から徹底的に数学と科学の教育を施します。当時の女性としてはかなり珍しい教育方針でしたが、これがエイダの才能を爆発させるきっかけになりました。

運命の出会いと「解析機関」
エイダが17歳の時、のちに「コンピュータの父」と呼ばれる数学者、チャールズ・バベッジと出会います。 バベッジが構想していたのが、蒸気で動く巨大な計算機「解析機関」。 これは、パンチカードで指示を与えて計算させるという、まさに現代のコンピュータの設計図のようなものでした。
多くの人が「すごい計算機」としか見ていなかった中、エイダはこの機械の真のポテンシャルに気づいてしまいます。
「これは、ただの計算機じゃない…!」と。
注釈がまさかの本体超え?世界初のプログラム誕生
エイダの功績が最も輝いたのは、ある論文の翻訳でした。
イタリアの数学者が書いた解析機関に関する論文を英語に訳す際、彼女は自分の考えやアイデアを「注釈」として大量に書き加えたのです。 その結果、注釈のほうが元の論文より2倍以上も長くなってしまいました。
そして、この注釈の中に、歴史を動かす記述が生まれます。それは、解析機関を使って「ベルヌーイ数」という数値を計算するための、具体的すぎるほど詳細な手順の記述。これが「世界初のコンピュータプログラム」だと言われています。
彼女が考案したプログラムの概念を、以下の表に示します。このプログラムの概念は、現代でも使われる基本的な考え方ばかりです。
| 概念 | 説明 |
|---|---|
| サブルーチン | よく使う命令をセットにして、いつでも呼び出せるようにしておくこと |
| ループ | 「〇〇の間は、これを繰り返して」と命令すること |
| ジャンプ | プログラムの途中で、別の命令にジャンプさせること |
さらに驚くべきは、エイダが「この機械は数字だけじゃなく、音楽を奏でたり、絵を描いたりもできるはず」と予見していたことです。 コンピュータが、計算だけでなくあらゆる情報を扱える「汎用マシン」になることを見抜いていたんですね。
後世への影響
エイダの業績は当時は十分に評価されませんでしたが、彼女の死後100年が経った20世紀に入り、コンピュータの歴史が研究される中で、再評価されることになります。 1979年には、彼女の功績を称え、米国国防総省が開発したプログラミング言語に「Ada」という名前が付けられました。
システム運用の現場では、日々新しい技術が登場しますが、その根底には、エイダ・ラブレスのような先人たちの情熱と探求心があります。
彼女の物語は、現代のエンジニアにとっても、新たなインスピレーションを与えてくれるのではないでしょうか。



