
K8sの「8」って何?Kubernetesの略称に隠された秘密
システム運用に携わっていると、よく「K8s」という文字列を目にしますよね。
コンテナ化されたアプリケーションを自動的にデプロイ、スケーリング、管理するためのオープンソースのプラットフォーム「Kubernetes」のことを指しているとは分かりつつも、「なぜKとsの間に8が入っているんだろう?」と、ふと疑問に思ったことはありませんか?
本日は、このK8sの謎について掘り下げてみましょう。
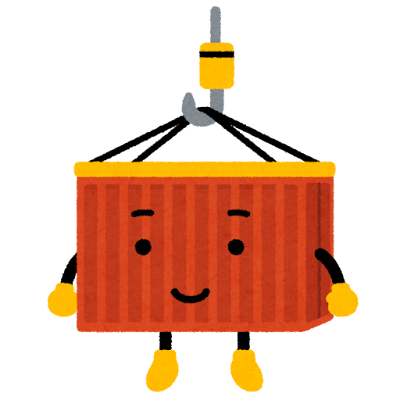
答えは「ヌメロニム(Numeronym)」
結論から言うと、この表記法は「ヌメロニム(Numeronym)」または数略語と呼ばれるものです。
…いきなり、聞きなれない単語が出てきましたね。
これは、少し長めの英単語の最初と最後の文字を残し、その間にある文字を文字数に置き換えて短縮する手法です。
Kubernetesの場合、「K」と「s」の間に「ubernete」という8つの文字があります。そのため、これを「8」に置き換えて「K8s」と略しているのです。 シンプルですが、面白い発想ですよね。

K8sだけじゃない、IT業界のヌメロニム
このヌメロニム、実はIT業界では昔からよく使われている手法です。皆さんも、知らず知らずのうちに目にしているかもしれません。
例えば、有名なものに「i18n」があります。これは「internationalization(国際化)」の略で、「i」と「n」の間にある18文字を省略したものです。他にも、私たちの身の回りにはこんなヌメロニムが存在します。
| 略語 | 元の単語 | 意味 |
|---|---|---|
| c14n | canonicalization | 正規化、カノニカリゼーション |
| a11y | accessibility | アクセシビリティ |
| m17n | multilingualization | 多言語化 |
| p13n | personalization | パーソナライゼーション |
| i14y | interoperability | 相互運用性 |
これらの略語を知っていると、海外の技術ドキュメントやブログ、SNSの投稿を読むときに役立つかもしれません!
なぜこんな略し方をするの?
一番の理由は、タイピングの手間を省き、コミュニケーションを効率化するためです。特に、Twitterのような文字数制限のあるプラットフォームや、チャットでのやり取りでは非常に便利です。
Kubernetesは、AWSの「Amazon EKS」 、Google Cloudの「Google Kubernetes Engine (GKE)」 、Microsoft Azureの「Azure Kubernetes Service (AKS)」 など、主要なクラウドサービスで基盤技術として採用されており、その影響力の大きさがうかがえます。
こうした背景もあり、エンジニアの世界ではK8sという略称が共通言語として広く浸透しています。
まとめ
日々の業務で当たり前のように使っている専門用語も、その由来を調べてみると意外な発見があるものです。K8sの謎が解け、少しスッキリしましたね。
今日もお仕事をがんばりましょう!



