
ガートナー、AIエージェントに関する見通しを発表 そのポイントとは?

2024年は生成AIの導入が進み、多くの企業で活用が進みました。AI技術の進化により、2025年にはAIエージェントという新たなシステムが普及すると見込まれています。
ガートナーは、2025年1月にAIエージェントに関する最新の見解をリリースしました※1。本リリースでは、AIエージェントの普及見込みと共に、その性能を見極めることの重要性についてもコメントされています。
今回は、AIエージェントについて初めて知る方に向けて、AIエージェントの概要やガートナーによる見通し、大手各社のAIエージェントサービスのリリース状況について詳しくご紹介します。
※1:Gartner「Gartner、急速に期待が高まっているAIエージェントに関する最新の見解を発表」
AIエージェントとは?

AIエージェントは、ユーザーのニーズに応じて自ら必要な行動を考え、調整し、与えられた目標を達成するシステムです。
Gartnerでは、AIエージェントを「デジタルおよびリアルの環境で、状況を知覚し、意思決定を下し、アクションを起こし、目的を達成するためにAI技法を適用する自律的または半自律的なソフトウェア」と定義しています。これをかみ砕くと、AIエージェントとは「特定の目標を達成するために、自律的に行動するAIシステム」と捉えられるでしょう。
2025年はAIエージェント元年
2025年はAIエージェント元年とも呼ばれています。この理由は、生成AIをはじめとした技術の発展によって、AIエージェントを実用レベルで導入できる年になると期待されているためです。
実際に、主要なベンダーではAIエージェントソリューションのリリースを公表しています。たとえばNECでは、Blustellarという名称にて、2024年11月にAIエージェントソリューションの提供を開始しました※2。他社も同様に、AIエージェントソリューションの開発・提供を進めており、2025年にはこれらのサービスを導入する企業が増えると予想されています。
※2参考:NECプレスリリース「NEC、高度な専門業務の自動化により生産性向上を実現するAIエージェントを提供開始」
AIの5段階進化モデルとは?
AIエージェントの位置づけを理解するためには、2024年10月にOpenAI社が公表した「AIの5段階進化モデル」を参考とするとよいでしょう。
OpenAIでは、AIの進化を以下の5段階に分けて整理しています。
| 概要 | |
| レベル1 | チャットボットなどの会話型AI |
| レベル2 | 人間レベルの問題解決能力を持つ推論AI |
| レベル3 | 自ら行動を起こせるエージェント |
| レベル4 | 発明を支援できる革新的なAI |
| レベル5 | 組織の業務を遂行できるAI |
現状のChatGPTをはじめとした生成AIはレベル1~2に相当します。基本的な会話に加えて、近年公開されたChatGPT o3などでは研究者レベルでの推論が可能となっています。
この次の段階として登場するのが、自ら行動を起こせるエージェントとしてのAIです。AIエージェントに対して目標を与えるだけで、目標達成に必要な行動を自動的に行ってくれるのが、レベル3としてのAIエージェントの位置づけとなります。
チャットボットやRPAとAIエージェントの違い
チャットボットやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)は、あらかじめ定義された作業手順を自動化するものです。一方でAIエージェントは、AIによって複雑なデータや状況を踏まえ、自律的に対応できる能力を持っています。ここが、両者の大きな違いです。
与えられた入力に合わせ、決められた通り動作するだけでなく、AIエージェントは状況を理解し、自ら「気を利かせながら」目的を達成するために必要なタスクやプロセスを行います。ユーザーとしての人間は、AIエージェントに目標やゴールを設定するだけで、必要な処理はAIエージェントが実施してくれます。
このように、AIエージェントは経験から学習して行動を改善する能力や、環境の変化や未知の状況に柔軟に対応する能力を有しています。
AIエージェントの仕組み
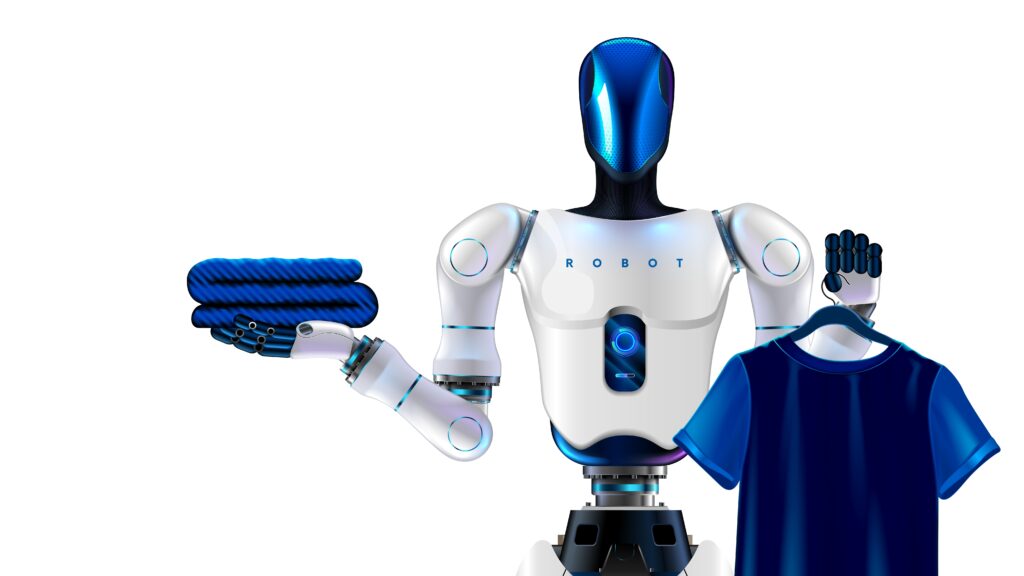
AIエージェントは大きく「環境からの情報収集」「意思決定」「動作」という3つの仕組みで構成されます。
環境からの情報収集
AIエージェントは、まず初めに環境から必要な情報を収集します。情報の収集にあたっては、センサー、カメラ、マイクロフォン、Web上のデータなど多岐にわたる情報源を利用します。
AIエージェントはこれらの情報源からデータをリアルタイムで収集し、環境の変化や現在の状況を把握します。これにより、AIエージェントは次の段階である意思決定に必要な情報を取得します。
たとえば、部屋を掃除するAIエージェントであれば、エージェントに備わっているカメラでまずどこに荷物が散らばっているのかを確認するイメージです。
意思決定
収集された情報を基に、AIエージェントは意思決定を行います。ここでは、機械学習アルゴリズムやディープラーニングが活用され、過去のデータや経験を基に予測や判断をします。
AIエージェントは複数の選択肢を比較し、最も効果的な行動を選択します。これにより、ユーザーの設定した目標に向かって最適な道筋を見つけることができます。
部屋を掃除するAIエージェントであれば、散らばっている荷物にぶつからないように、最適に元の位置に荷物を運ぶための経路を分析するイメージです。
動作
最後に、意思決定された内容に基づき、具体的なアクションを実行します。目的に応じて、物理的なロボットの操作や、ソフトウェア上でのタスク実行などを行います。
AIエージェントはこの段階で、実際に環境に働きかけ、設定された目標を達成するための動きを開始します。また、動作の結果をフィードバックとして取り込み、次回以降の意思決定に役立てていきます。
部屋を掃除するAIエージェントであれば、備わっているアクチュエーターや車輪などを動作させ、荷物をピックアップし、元の位置に戻していく作業を行います。
ガートナーによるAIエージェントの見通し
AIエージェントの普及に関して、ガートナーではAIエージェントの将来性や現時点での性能を以下のように推測しています。
AIエージェントは2028年までに60%の企業で導入
2024年後半から「AIエージェント」というキーワードの市場認知が急速に拡大しており、2025年以降段階的にAIエージェントが普及していくことが見込まれています。
2028年までに、日本企業の60%はAIエージェントによって機械的な業務に関するタスクの自動化を実現するとガートナーは予想しています。
AIエージェントは万能ではない
一方で、AIエージェントは必ずしも万能の道具ではないということも指摘されています。
ガートナーのリサーチャーによれば、企業はAIエージェントについて「即座に効果を発揮する高度なAI」や「全ての業務を円滑に遂行するソフトウェアやシステム」の登場と捉えるべきではないとされています。
何も設定せずに適切に対応できるAIエージェントは、現段階では存在していません。AIエージェントを導入したいと考える企業は、ベンダーが提供する「AIエージェントのフレームワーク」を使用し、特定のタスクに対応するように設定・開発する必要があります。
AIエージェントの導入を検討する前に、企業はまず現実を正確に把握することが重要です。全ての企業は、ベンダーに丸投げでPoCを依頼するのではなく、自社で体験や学習を行い、事前にAIエージェントの現実的な能力を強化することがポイントであるとしています。
このように、AIエージェントは必ずしもあらゆる業務に対応できる万能の道具ではないということに留意が必要です。自社の業務のうち、現在の技術の中で何をカバーできるのか、個別に検証していく必要があります。
AIエージェントの製品動向

以下では、主要なベンダーが提供するAIエージェントの製品動向をご紹介します。なお、以下の内容は2025年2月時点の内容となります。
NTTデータ
NTTデータでは、オフィスワーカーの生産性向上と付加価値業務へのシフトを目指し、生成AI活用エージェントサービス「SmartAgent」の提供を開始しています。SmartAgentはAIエージェントとして、利用者の指示に従って自律的にタスクを抽出・整理・実行していきます。
同社では、SmartAgentの段階的な機能拡充を予定しています。まず第一弾のサービスとして、「LITRON Sales」を2024年11月から提供開始しました。LITRON Salesは営業領域でのデータ入力作業や提案書作成などのタスクを自律的に実行するAIエージェントです。同社では今後も、様々な領域においてAIエージェントサービスの提供を続けていくとしています。
NTTデータ「AIエージェントを活用した新たな生成AIサービスを提供開始」
富士通
富士通では、人とAIが協力して難易度の高い業務を推進できるAIサービス「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を開発し、2024年10月より提供を開始しています。
Fujitsu Kozuchi AI Agentは、会議中に情報の共有や施策の提案を行うことができる機能を備えています。会議の中でリアルタイムにデータ分析を行い、適切なタイミングで結果を提示することができます。
同社では、今後生産管理や法務などの業務に特化したAIエージェントも順次提供していく予定としています。
富士通「AIが人と協調して自律的に高度な業務を推進する「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を提供開始」
NEC
NECは、生成AIを含む様々なAIやITサービスを連携させ、自律的に業務を遂行するAIエージェントを2025年1月から提供開始すると発表しています。NECのAIエージェントは、ユーザーが依頼したい業務を入力すると、AIがタスクを分解し、最適なプロセスを設計して自動実行します。
同社では、まず経営計画、人材管理、マーケティング戦略などの自動化を対象としたサービスを提供予定です。たとえば「キャリア採用者の育成戦略」を依頼すると、情報収集から育成計画書の作成までを自動で行うことができます。
NECは、このAIエージェントを活用して業務の効率化と生産性向上を目指し、2025年度末までに500億円の売り上げを目指すとしています。
参考:NEC「NEC、高度な専門業務の自動化により生産性向上を実現するAIエージェントを提供開始」
Cognition
日本企業ではありませんが、米国Cognition社のAIエージェントサービスについても取り上げます。2023年に設立された同社では、2024年3月に世界初の完全自律型AIソフトウェアエンジニア「Devin」をリリースしました。
Devinは、Webサイトやスマホアプリの作成からバグ修正など、プロジェクトをほぼ自動で進めることができます。多くの意思決定を必要とする複雑なソフトウェア開発の計画から実行までが可能です。
Devinは開発に必要な情報を収集し、時間をかけて学習し、バグの修正まで対応可能です。さらに、人間とのコラボレーションも可能であり、リアルタイムで進捗状況を報告し、フィードバックを受け入れ、設計や開発方法を調整できます。
Cognition「Introducing Devin, the first AI software engineer」
このように、各社が新たなAIエージェントサービスをリリースし始めている状況にあります。今後、製造や営業、事務などの機能特化型のAIエージェントサービスが2025年中にもリリースされていくと思われます。
企業がAIエージェントを導入するメリット

それでは、企業がAIエージェントを導入するメリットはどのようなところにあるのでしょうか。
生産性向上
AIエージェントの導入により、企業は業務の自動化と効率化を実現できます。従来、RPAなどで部分的に自動化されていた業務も、プロセスの検討から実行まで、全て自動化できる可能性があります。
たとえば、DevinのようなAIエージェントは、ソフトウェア開発の進行をほぼ自動化可能です。これにより、開発プロジェクトのスピードが向上し、リソースの有効活用も実現します。
意思決定のサポート
AIエージェントは大量のデータを迅速に分析し、適切な意思決定をサポートする役割も果たします。AIはリアルタイムで進捗状況を報告し、フィードバックを受け入れ、最適な設計や開発方法を提案します。これにより、経営層やプロジェクトマネージャーはより迅速かつ正確な意思決定が可能となり、リスクを最小限に抑えることができます。
顧客満足度の向上
顧客対応の効率化にも貢献できるのがAIエージェントです。たとえば、カスタマーサービスにAIを導入することで、顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応できます。
AIエージェントは24時間体制でサービスを提供できるので、顧客の利便性が向上します。満足度を高め、ブランドロイヤルティの強化にもつなげられるでしょう。
まとめ
今回は、2025年に注目すべきAIエージェントについてその仕組みから企業における導入メリット、主要各社のサービスリリース状況など、詳しくご紹介しました。
先進的な取り組みを進められている企業においては、AIエージェントは確実に導入を検討するサービスとなると思われます。一方で、各社のAIエージェントサービスは現時点で部分的な提供にとどまっており、今後の追加リリースが待たれる状況です。各社の動向をウォッチしていくことをおすすめします。



