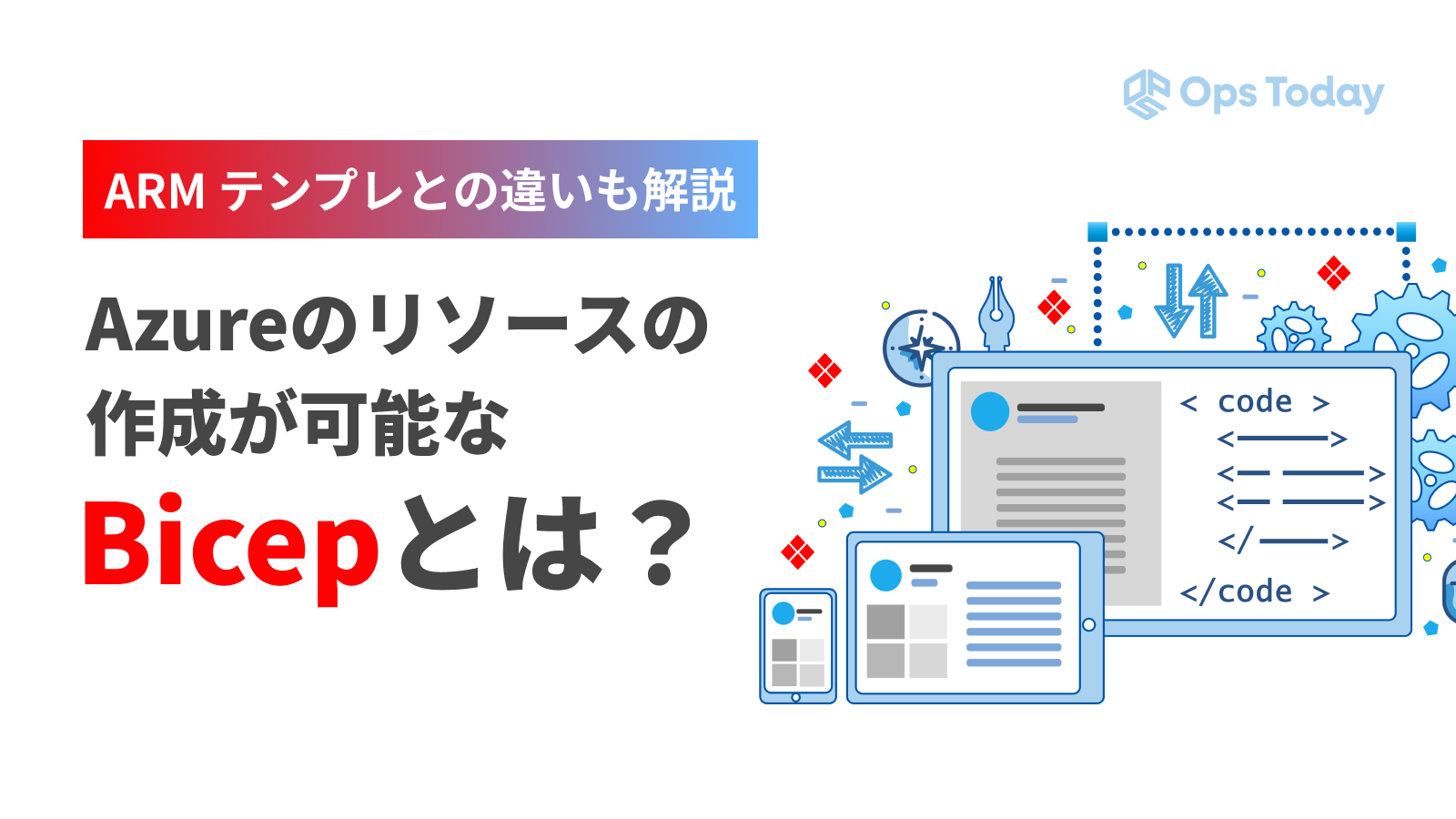
Azureのリソース作成が可能なBicepとは?ARM テンプレートとの違いを比較!
クラウドインフラ管理を効率化する「Bicep」は、Azureリソースを簡単に作成・管理できるIaC(Infrastructure as Code)ツールです。ARMテンプレートの代替として、より簡潔な構文と高い可読性を提供します。
本記事では、Bicepの特徴、ARMテンプレートや他のIaCツールとの違い、具体的なユースケース、インストール方法を詳しく解説します。Azureを活用する開発者やクラウドエンジニア必見の内容です。
Azure向けのIaCツール「Bicep」とは?
Bicepは、Microsoft Azure向けのIaCツールで、クラウドリソースの定義、管理、デプロイを効率化します。ARMテンプレートの煩雑さを解消する目的で開発され、シンプルかつ直感的な独自言語を採用しています。
JSON形式で記述されるARMテンプレートとは異なり、Bicepは簡潔で読みやすい構文を持ち、コード量を大幅に削減できます。また、Azure CLIやPowerShellとネイティブに統合されており、スムーズなデプロイが可能です。以下のような特徴があります。
- Azure CLIやPowerShellとネイティブに統合し、スムーズなデプロイを実現。
- 型安全性やモジュール化を標準サポート。
- ARMテンプレートに自動コンパイルされ、完全な互換性を確保。
ユースケースとしては、例えば小規模なWebアプリのデプロイ(例:Azure Functions)や、大規模なエンタープライズ環境でのリソース管理(例:仮想マシンクラスタ)などがあげられます。Bicepは型安全性やモジュール化を標準でサポートされているため、開発者にとって扱いやすいツールと言えるでしょう。
IaC(インフラストラクチャコード)とは?
IaC(Infrastructure as Code)は、インフラの設定や管理をコード化する手法です。こちらを用いることで手動作業を排除し、インフラのプロビジョニングや構成を自動化できます。コード化されたインフラは、バージョン管理が可能で、一貫性を保ちながら迅速な変更が行えます。
従来、インフラ構築はGUIベースの手動作業が一般的でしたが、IaCの登場でスクリプトを用いた効率的なインフラ管理を可能にします。以下は、IaCによるメリットです。
- ミスの削減:手動設定によるエラーを防止。
- 再現性の向上:同一環境を繰り返し構築可能。
- 迅速なスケールアップ:需要に応じたリソース追加が容易。
BicepやTerraform、CloudFormationは、こうしたIaCを実現するツールの代表例です。
Bicepと他のIaCツールの違い
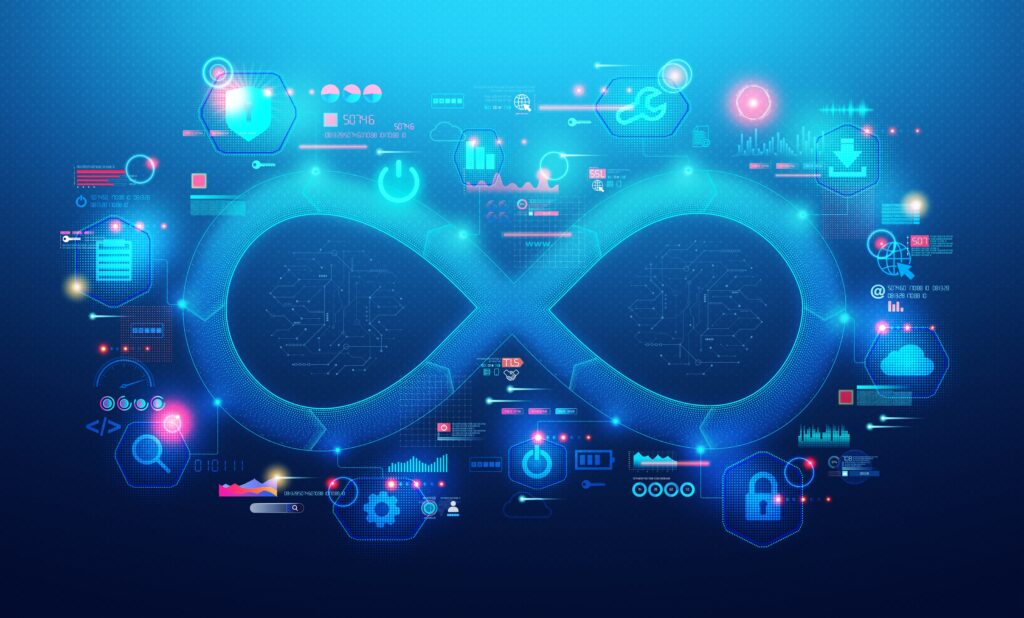
BicepやTerraform、CloudFormationはいずれもIaCツールですが、対象範囲や操作性が異なります。
terraform
BicepとTerraformはどちらもIaCツールですが、対象範囲や操作性が異なります。Terraformは複数のクラウドプロバイダー(AWS、Azure、Google Cloudなど)をサポートし、マルチクラウド環境の構築に適しています。一方、BicepはAzure専用であり、Azureサービスとの密接な連携が特徴です。
また、TerraformはHCL(HashiCorp Configuration Language)を採用し、シンプルながら柔軟性の高い構文を持っています。一方で、BicepはAzureリソースマネージャー(ARM)との互換性が強みで、Azure固有の機能を活用しやすいのがメリットです。
Azureに特化したプロジェクトでは、Bicepが適しているでしょう。
CloudFormation
CloudFormationはAWS専用のIaCツールで、AWS環境におけるリソース管理を効率化します。一方、BicepはAzure専用のツールであり、これらは異なるクラウドプロバイダーの環境に対応しています。構文のシンプルさでは、BicepがCloudFormationを上回ります。
CloudFormationはJSONまたはYAML形式で記述しますが、入れ子構造が複雑になる傾向があります。対して、Bicepは簡潔な独自言語で書かれており、理解し易い構造となっています。
使用するクラウドが異なるため、適切な選択はプロジェクトの要件によると言えるでしょう。
BicepとARM テンプレートの違い
BicepとARMテンプレートはどちらもAzureリソース管理を目的としていますが、記述方法や操作性に大きな違いがあります。BicepはARMテンプレートの課題を解消し、簡潔で読みやすい構文を提供する次世代ツールです。
使用言語の違い
BicepとARMテンプレートの主な違いは、使用言語の形式にあります。ARMテンプレートはJSON形式で記述されるため、構文が冗長で入れ子が深くなりがちです。特に複雑なリソース構成を記述する場合、手作業で編集するのは手間がかかります。
一方、Bicepは独自の宣言型言語を採用しており、ARMテンプレートの上位レイヤーとして設計されています。この言語は簡潔で、リソースの構成を直感的に記述できます。さらに、Azureリソースマネージャーと完全に互換性があるため、Bicepで記述したコードはデプロイ時にARMテンプレートに自動コンパイルされます。
この違いにより、Bicepは学習のしやすさと保守性で優位に立っています。
拡張性の違い
拡張性においても、BicepはARMテンプレートより優れています。ARMテンプレートで条件分岐やループ処理を実装する場合、複雑な構文を用いる必要があります。これに対し、Bicepではシンプルな構文で条件分岐やループを簡単に記述できます。
たとえば、リソースの数や構成を動的に変更するシナリオでは、Bicepのループ機能を活用することで、冗長な記述を避けながら柔軟なテンプレートを作成できます。また、モジュール機能を利用してコードを分割し、再利用性を高めることが可能です。これにより、大規模なインフラ構成でもコード管理が容易になります。
拡張性を重視するプロジェクトでは、Bicepが最適な選択肢と言えるでしょう。
利用難易度・学習コスト
学習コストは、BicepはARMテンプレートに比べて有利です。ARMテンプレートはJSON形式の記述で柔軟性があるものの、構文が複雑で初心者には扱いにくい側面があります。
一方、BicepはAzureリソースを扱うために特化した直感的な構文を採用しており、初学者でも理解しやすい設計です。また、Microsoftが公式に提供するBicepのドキュメントやチュートリアルも充実しており、学習環境が整っています。
再利用性とモジュール化
再利用性とモジュール化の面でも、Bicepは優れた機能を備えています。Bicepでは、リソース定義をモジュール化することで、複数のプロジェクト間で簡単に再利用できます。
モジュールを作成するとき、パラメータを柔軟に設定できるため、異なる環境や要件に応じて同じコードを利用することが可能です。
ARMテンプレートでもネストされたテンプレートを使用することで再利用は可能ですが、構文が複雑で管理が困難になる場合があります。一方、Bicepのモジュールは単純な記述で、他のBicepファイルを簡単に呼び出せるため、メンテナンス性が大幅に向上します。
このような再利用性の高さは、長期的なコードの保守やスケーラビリティにおいて重要な利点となります。
BicepとARM テンプレート、どちらを利用するべきか

新規プロジェクトではBicepが推奨されますが、既存のARMテンプレート資産がある場合、移行計画を考慮してARMテンプレートを引き続き活用する選択もあります。
新規プロジェクトの場合はBicepを利用
新規プロジェクトを開始する場合、Bicepを利用するのが賢明です。BicepはAzureリソースの構成を簡潔に記述できるため、開発スピードを向上させます。また、Azureリソースマネージャーとの互換性が保証されており、最新のAzure機能にも迅速に対応します。
さらに、モジュール化やパラメータ化が容易なため、再利用性が高く、チームでの作業にも適しています。Visual Studio CodeのBicep拡張機能を活用することで、コードの自動補完やリアルタイムのエラーチェックが可能になり、開発効率がさらに向上します。
特に、シンプルな構文とツールサポートの充実により、初心者にも扱いやすいのが特徴です。
既存のARMテンプレートがある場合はARM テンプレート
既存のARMテンプレート資産がある場合、引き続きARMテンプレートを使用するのが適切なケースも多いでしょう。
ARMテンプレートは長期間にわたりAzureリソースの管理に用いられてきたため、企業のシステムやCI/CDパイプラインに深く統合されている場合がよくあります。これらの既存資産を短期間でBicepに移行するのは、コストやリスクが伴うため慎重な計画が必要です。
ARMテンプレートの利点は、Azureサービスの包括的なサポートと、多くの既存のドキュメントやコミュニティリソースが利用できる点です。また、すでに運用中のインフラで問題なく動作しているテンプレートであれば、無理に移行せず、現状維持のまま活用する選択肢も妥当です。
高度な自動化やCI/CDパイプラインとの統合はBicepを利用
高度な自動化やCI/CDパイプラインとの統合を目指すプロジェクトでは、Bicepの利用が推奨されます。
Bicepは、Azure CLIやAzure DevOps、GitHub Actionsとシームレスに統合可能であり、デプロイプロセスを効率化します。さらに、Bicepファイルは簡潔で可読性が高いため、コードレビューや共同作業がスムーズに進みます。
Bicepのモジュール機能は、再利用性を高めるだけでなく、CI/CD環境での構成管理を簡素化します。たとえば、モジュール化したBicepコードを複数の環境(開発、テスト、本番)で使い回すことで、環境ごとの整合性を保ちながらデプロイを自動化できます。
Bicepのインストール方法と使い方
BicepはAzure CLIを使用して簡単にインストールできます。ここではインストール手順と、実際にAzureリソースをデプロイする方法を解説します。
インストール方法
Azure CLIを利用して次のコマンドを実行します。
| az bicep install |
インストール後、以下のコマンドでインストールが正しく行われたことを確認します。
| az bicep version |
Azure CLIを利用している場合、最新バージョンではBicepが自動的に組み込まれていることもあります。macOSユーザーの場合、Homebrewを使ったインストールも可能です。
| brew tap azure/bicep brew install bicep |
また、Visual Studio Codeを使用して開発する場合は、Bicep拡張機能をインストールすることで、コード補完やリアルタイムのエラーチェックが利用可能になります。これにより、効率的な開発環境が整います。
リソースグループをデプロイしてみる
Bicepをインストールしたら、実際にAzureリソースをデプロイしてみましょう。まず、以下のようなBicepファイルを作成します。
main.bicep
| resource myResourceGroup ‘Microsoft.Resources/resourceGroups@2024-12-27’ = { name: ‘MyResourceGroup’ location: ‘japaneast’ } |
このファイルを保存したら、Azure CLIを使ってデプロイします。以下のコマンドを実行してください。
| az deployment group create –resource-group MyResourceGroup –template-file main.bicep |
デプロイが成功すると、AzureポータルまたはAzure CLIでリソースグループを確認しましょう。また、パラメータファイルを利用することで、コードの柔軟性をさらに高めることが可能です。例えば、リソースグループ名やリージョンを動的に変更できます。
まとめ
BicepはAzureリソースを効率的に作成・管理できる次世代のIaCツールで、シンプルな構文と高度なモジュール化機能が特徴です。特に新規プロジェクトやCI/CDパイプラインへの統合が求められるシナリオでは、Bicepの利用が大いに役立つでしょう。また、既存のARMテンプレートとの互換性があるため、段階的な移行も容易です。
Bicepを活用する際には、リソースのセキュリティを確保することが重要です。「BicepでAzureリソースのコード作成、Checkovでセキュリティチェックを行う方法」は、こちらの記事を参照してください。



