
2024年10月公表「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」を解説

2024年10月に経済産業省から公表された「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」は、デジタル社会の基盤を強化するための重要な指針がまとめられています。本内容は今後のデータセンター整備、広域ネットワーク整備に関する政府方針となるものであり、企業にとって影響があるものです。
そこで今回は、この中間報告書の主要な内容とその背景について解説します。
デジタルインフラとは?

そもそも、デジタルインフラとは何なのでしょうか?
デジタルインフラとは、現代社会に必須となっている情報技術を利用するために重要となる、データセンターや海底ケーブルなどの通信ネットワーク、クラウド環境などを指す言葉です。デジタルインフラについての理解を深めるため、ここでは近年のデジタルインフラに関する動向を整理します。
デジタルインフラが必須となっている現代社会
デジタルインフラは現代の情報社会において必須のものです。通信ネットワークが無ければ人々はインターネットにアクセスできず、オンラインショッピングやリモートワーク、遠隔医療など、さまざまなサービスが利用不可能となります。また、企業はデータセンターやクラウド環境を活用することで、効率的に事業を運営し、グローバルな競争力を維持・向上させています。
このように、デジタルインフラは現代社会のあらゆる側面において重要な役割を果たしており、その整備は避けて通れない重要な取り組みとなっています。
デジタルインフラに関する国の取り組み
このように重要度の高いデジタルインフラの整備は、総務省・経済産業省を中心に国家的に取り組みが進められています。
2021年より、総務省・経済産業省では「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合」を開催し、5Gや通信ネットワーク、データセンター等の整備方針について検討を進めています。本検討結果は2022年に「中間とりまとめ1.0版」として公表されました。その後改訂が行われ、2023年には中間とりまとめ2.0版」が、2024年10月には最新版である中間とりまとめ 3.0版」が公表されています。
「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」検討の背景

以下では、デジタルインフラ整備に関するこれまでのとりまとめ状況を整理しつつ、最新の3.0版公開の背景をまとめます。
これまでの検討内容
動画トラフィックの急増やクラウド化、AIの進展により、データセンターや海底ケーブルなどのデジタルインフラへの需要が増え続けているなか、有識者会合では2022年に以下の方針を取りまとめました。
- 自然災害時等へのレジリエンス強化
- 地方の再生可能エネルギーの効率的活用
- 地方で生まれるデータの「地産地消」を可能とする通信ネットワーク等の効率化
その後有識者会合では検討が続けられ、2023年には「中間とりまとめ2.0」が公表されています。中間とりまとめ2.0では、日本の地理的優位性を活かした国際的なデータ流通のハブ機能を強化するため、北海道や九州に新たなデータセンターの中核拠点を整備する方針や、国際海底ケーブルの多ルート化を促進する方針を整理しました。
これまでの政策実行状況
総務省と経済産業省では、この「中間とりまとめ」および「中間とりまとめ2.0」に基づき、データセンターの分散立地に向けた施策を進めてきました。具体的には、北海道や九州など7カ所のデータセンター設立への支援や、国際海底ケーブルの多ルート化の支援などが行われています。
また、経済産業省では2023年より北海道苫小牧市のデータセンター事業の支援を行っています。このような政策により、データセンターの東京圏・大阪圏への集中が改善され、北海道や九州が新たな中核拠点として整備されつつあります。
また、民間事業者との連携も進んでおり、官民協力によるデジタルインフラの強化が期待されています。その他の地域でも2024年度以降に新たなデータセンターの計画が進んでいます。
このように、「中間とりまとめ」および「中間とりまとめ 2.0」での提言に基づく取り組みが進んでいるところです。
「3.0版」での検討内容
このような状況の中、近年の見逃せない動向として、AIの爆発的な進化が挙げられます。世界全体および日本国内でも、クラウド化やAIの導入・進展と相まってデータセンターへの新規投資が拡大しています。
特に生成AIの台頭に伴うデータセンターの役割や用途の変化と大規模化の動向に注目が必要です。2020年頃から、クラウド用途の数十MW規模のハイパースケール型データセンターの整備が増加してきました。今後はAIの学習や推論に使用するための数百MW~GWクラスのデータセンターの整備が見込まれています。
このように、生成AIの登場によりここ1年余りでデジタルインフラ環境が変化し、これまでの延長線上で捉えることは難しい変革期を迎えています。
また、日本の社会的な課題に目を向けると、人口減少や少子高齢化が深刻化しています。特に地方においてこの問題の進行が顕著であり、地域社会の維持や地方創生、ひいては国全体の成長の観点から、AIなどのデジタル技術による地域DX(デジタルトランスフォーメーション)の実現が重要性を増しています。そのため、地域DX実現においてエコシステムの核となるデータセンターへの期待も高まっています。
このような背景を踏まえ、総務省と経済産業省は、2024年5月から有識者会合を再開し、データセンターの整備について最新の市場や技術の動向を踏まえ、用途や規模に応じた立地要件や拠点整備の方向性を再検討しました。本検討結果が、「中間とりまとめ3.0」として整理されたものです。
デジタルインフラ整備の方向性
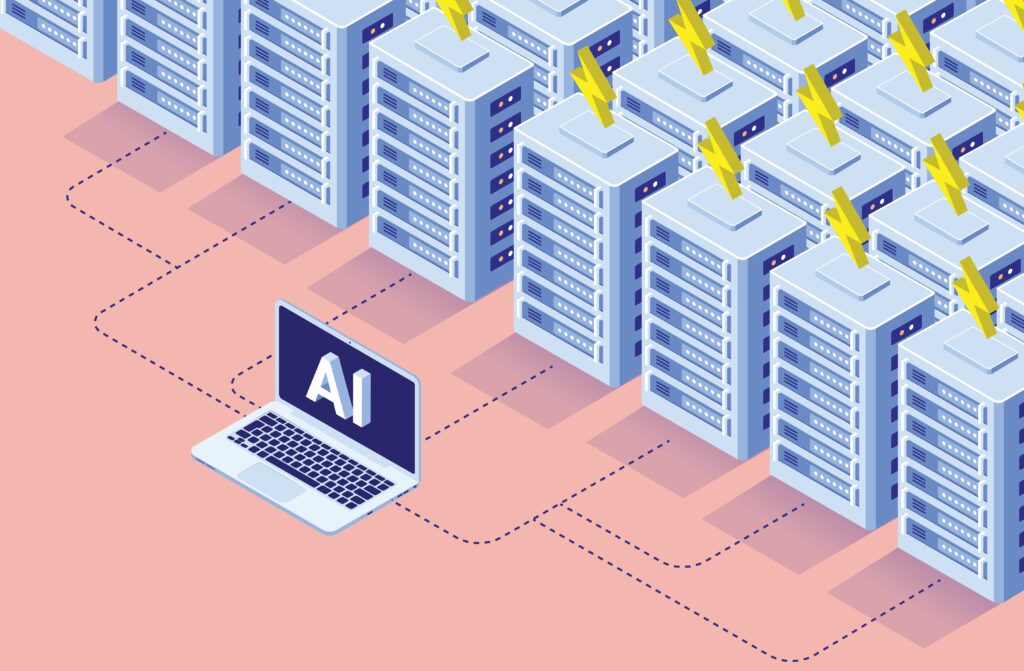
「中間とりまとめ3.0」では、以下のように4つの観点からデジタルインフラ整備の方向性を定義しています。ここでは、各観点の概要をご紹介します。
- データセンターの分散化
- AI活用に耐えうる高性能データセンター・ネットワークの整備
- 国家間の海底ケーブルの分散化・多ルート化
- 持続可能性を意識したデータセンターの整備
データセンターの分散化
近年の技術的な進化を踏まえ、AIは日本の社会的な課題の解決や産業競争力の確保・強化に貢献することが期待されています。
AIの活用に不可欠なのが高性能データセンターです。そこでデジタルインフラの整備方針として、遅延が許容される学習用途と低遅延が求められる推論用途を区別しつつ、データセンターの用途や規模に応じた設置を進めることとしています。
さらにポイントとなるのが、データセンターの分散化です。地方のデータセンター整備を進めることは、AI活用や高度なサービスを地域でも東京や大阪と同様に実現するための基盤となります。国や地方自治体、民間事業者が連携し、先行的にデジタル実装を進める地域からデータセンターの整備が進められる予定です。
さらに、地政学的な状況も踏まえ、近隣諸国との協力も進められます。データセンターの地域分散を推進するための政策支援を検討し、電力インフラや通信ネットワークの課題も踏まえ設置地域を背停止、整備を促進していきます。
AI活用に耐えうる高性能データセンター・ネットワークの整備
産業競争力の強化やエネルギー効率の向上のため、次世代光技術や低消費電力の半導体技術、AIチップの開発が求められています。この中でも、特にオール光ネットワークの活用が有力視されています。
オール光ネットワークとは、光の特性を最大限活用したネットワークを指します。オール光ネットワークを実用化できれば、その低遅延性と低消費電力でデータセンターの設置地域を広げ、脱炭素化に寄与することができます。このような背景から、本取りまとめではデータセンターの整備をオール光ネットワークの展開と連動させていく方針を打ち出しています。
併せて、生成AIのライフサイクルや負荷分散のための計算基盤に関する研究開発も進められています。これらの技術を活用しつつ、地域へのデジタル投資の持続可能性も高めるべき、とされています。
今後、これらの技術開発が進み、複数のデータセンターが効率的に接続され、運用されることが期待されます。
国家間の海底ケーブルの分散化・多ルート化
本取りまとめでは、国際海底ケーブルについても分散立地が重要であることが指摘されています。
首都直下地震や南海トラフ地震などの災害への対応や地政学的リスクを考慮し、デジタルインフラの東京圏・大阪圏集中を是正する必要があります。具体的には、海底ケーブルの多ルート化による欧米やアジア太平洋との接続性強化を目指す方針を掲げています。
このような方針の元、現在では房総半島や志摩半島に集中している国際海底ケーブルの陸揚局を、他の地域に分散させる方向性が示されています。前述したデータセンターの分散立地とオール光ネットワークの連携も踏まえ、欧米・アジアとの接続性を強化してデータ流通のハブとして、国際的なAIファクトリーとしての地位を確立することが目標とされています。
持続可能性を意識したデータセンターの整備
電力の輸送コストと比較すると、情報の通信コストの方が安価となります。そこで、データセンターを需要地近くに設置するよりも、電力インフラ近辺に設置したうえで、データの処理結果を通信ネットワークで需要地に伝送する方法が効果的です。
AI用の大規模データセンターは多くの電力が必要であり、立地選定においては電力インフラの有無が重要です。よって、本取りまとめでは脱炭素電源の確保と既存の電力インフラを活用できる場所や、将来的に電力インフラが確保される見込みのある場所にデータセンターを設置する方針を掲げています。いわゆるGX(グリーントランスフォーメーション)政策とも連動し、環境面を意識したデータセンターの整備を進めていくこととされています。
持続可能なデータセンターとAIの社会実装を推進するためには、省エネ技術の研究開発・実装を国として促進する必要もあります。また、各事業者のエネルギー消費効率の現状や改善策を可視化し、他社と比較し効率改善を促すことも必要な政策として指摘されています。
本方針が企業に与える影響

それでは、これらの方針は企業にどのような影響を与えるのでしょうか。
以下では「データセンターの拠点選定の観点」「AI活用の観点」「脱炭素化の観点」の3つからご紹介します。
データセンターの拠点選定の観点
これまで、データセンターの立地は首都圏の特定地域に集中していました。すでに分散立地に向けた政策も進められていますが、今後データセンターの立地はさらに地方拠点に分散化されていくと思われます。
この恩恵を特に受けられるのは、各地方の企業と考えられます。自社に近いデータセンターを利用できることは、企業にとって大きなメリットとなります。具体的には、データセンターの立地が近いことにより低遅延化が見込めることや、通信コストの削減が期待される点などがメリットです。さらに、トラブル対応やメンテナンス対応、監査対応などでデータセンターへ実際に足を運ぶのも、物理的な距離が近ければ効率的に行うことができます。
今後、特に地方の企業において、データセンター選びの際にこれらの効率性・利便性を高められる選択肢を取りやすくなると思われます。
AI活用の観点
AIの学習や推論を行う際に、大きく自前のサーバーやPCなどを利用する方法と、データセンター上で実施する方法の2つが存在します。今後、AI用途向けに整備されたいわゆる「AIデータセンター」の整備が進み、AI実装時にデータセンターを利用するという選択肢がとりやすくなると思われます。
AIの学習や推論は、大規模に計算リソースやネットワークリソースを消費する取り組みとなります。よって、データセンターの効率性は非常に重要な観点です。エネルギー効率性の高いデータセンターを選ぶことで、AI処理のための計算リソースの使用が最適化され、コスト削減につながります。
また、データセンターと利用拠点とのネットワーク接続が高速で安定していることも重要です。データ転送速度が遅いと、AI処理のスピードに影響を与え、全体のパフォーマンスが低下する可能性があります。
このように、AIの活用においてはAI向けに整備されたデータセンターの利用が重要となりますが、今後AI向けのデータセンターが進んでいき、企業においてはより安価にAIを活用できるチャンスとなります。
脱炭素化の観点
システムの利用によるエネルギー消費量は増加の一報をたどり、近年では省エネ・脱炭素化の観点からシステムのエネルギー消費量削減の取り組みも進められています。
企業においても脱炭素化に向けた取り組みが求められる中、自社が利用するシステムのエネルギー効率化の取り組みは企業のアピールポイントにもなります。
今後、再エネを利用したデータセンターや、エネルギーの高効率化を実現したデータセンターの普及が進んでいくと思われます。これらのデータセンターを活用することで、自社の脱炭素化に向けた取り組みを進めることができます。
まとめ
この記事では、2024年10月に公表された「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」について、主要な内容とその検討背景について解説しました。
デジタル技術の利活用は今後も進んでいくと思われ、それを支えるデジタルインフラの重要性は高まり続けます。企業においては、自社のIT基盤の整備やAI活用の観点で、これらのデジタルインフラを利用することとなります。今後、具体的にどのようにデータセンター整備やネットワークの敷設が進んでいくかを注視していくべきです。



