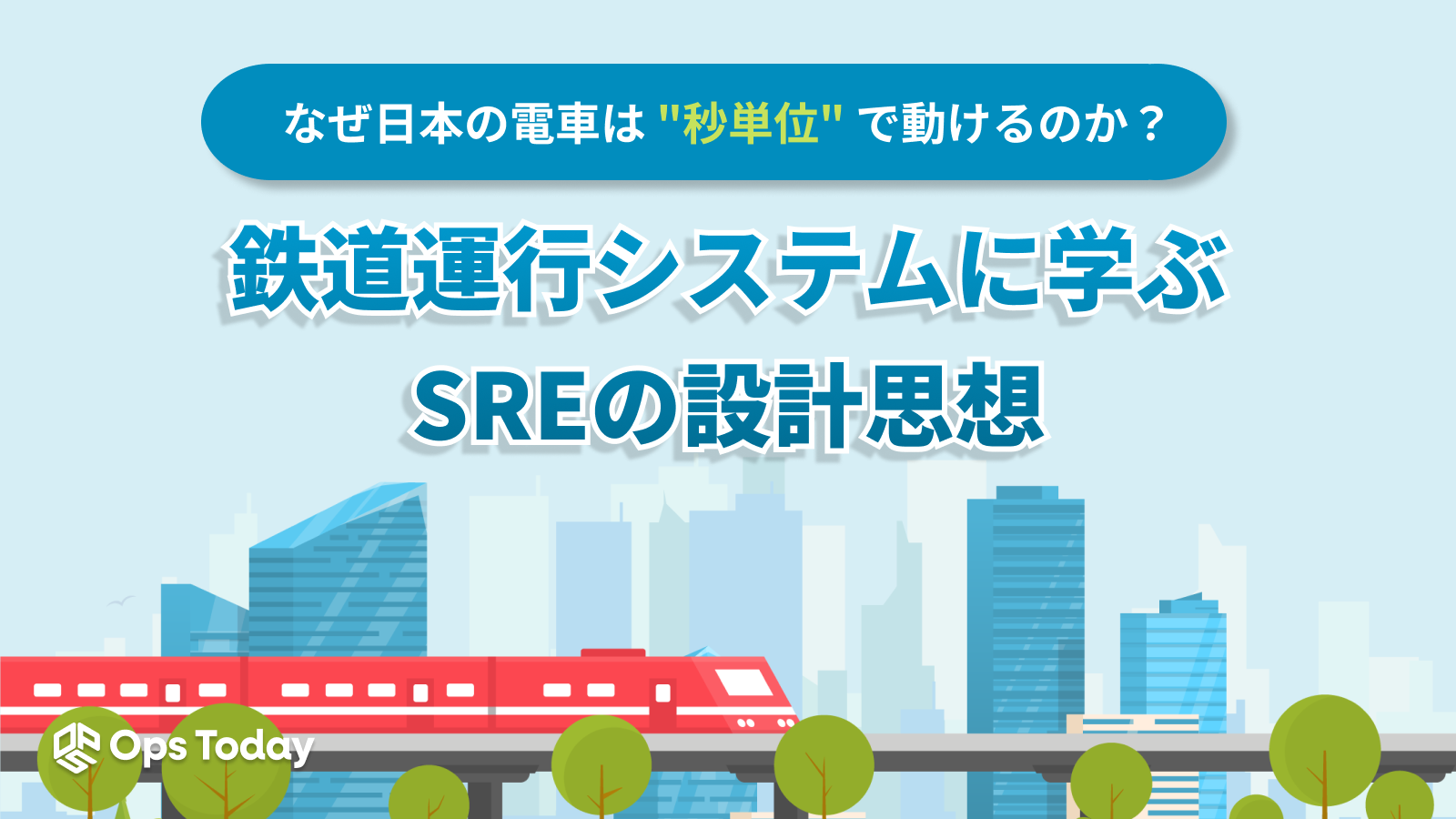
なぜ日本の電車は”秒単位”で動けるのか?鉄道運行システムに学ぶSREの設計思想
今年に入ってからテレワークが廃止され、毎日出社する日々。先日、朝の通勤ラッシュで駅のホームに立っていると、ふと電光掲示板が目に入りました。
━ 次の電車 8:22 発。
その後、寸分の狂いもなく滑り込んでくる電車。
当たり前すぎて普段は気にも留めませんが、数分、時には秒単位の正確さで運行される首都圏の鉄道は、世界でも類を見ない高信頼性・高可用性を実現した巨大システムとして有名です。

信号やポイントの切り替え、優等列車の待避…。まるで、巨大なコンピュータ上で無数のプロセスが動いているかのようです。
調べてみると、鉄道の運行システムは、我々SREが学ぶべきことの宝庫でした。今日は、そんな日本が世界に誇る鉄道システムに隠された、システム設計の哲学について少しお話ししてみたいと思います。
信号システムから学べる「確実な排他制御」
列車の安全運行の根幹をなすのが、閉塞(へいそく)という考え方です。
これは、一つの線路区間には同時に一つの列車しか入れないようにする仕組みで、列車の追突という最悪の事態を防ぎます。いわば、データベースにおけるトランザクション処理の「ロック(排他制御)」と同じ考え方です。

ここから学べること
ここから学べるのは、「クリティカルなリソースは、シンプルかつ絶対的なルールで保護すべし」という点です。「1閉塞区間に1列車」という単純明快なルールが、複雑なダイヤグラムで運行される大規模システムの安全性を根底から支えています。
SREに活かせるポイント
我々のシステムにおいても、複数のサーバーやプロセスが同時に書き込む可能性がある設定ファイルや共有メモリは、まさに「閉塞区間」です。意図しない競合は、データ破損やシステムダウンに直結します。
この学びから、共有リソースへのアクセス制御の設計を見直し、より堅牢な排他制御の仕組みを導入する、もしくはそもそも共有リソースに依存しない設計を検討する、といったアクションに繋げられます。
待避線から学べる「賢いリソース管理」
普通列車に乗っていると、特急や快速列車を先に通すために駅で数分間停車することがあります。この「待避」で使われるのが、本線とは別に設けられた「待避線」です。

ここから学べること
待避線からは、システム全体のスループットを最大化するためには、リクエストに優先順位をつけ、リソースを賢く割り当てることが重要だ、という点が学べます。
すべてのリクエストを平等に扱うのではなく、ビジネスインパクトの大きい処理(優等列車)を優先することで、全体の効率とユーザー満足度を向上させているのです。
SREに活かせるポイント
例えば、ユーザーからのリクエストを処理するAPIと、時間のかかるバッチ処理を同じリソースで実行していませんか?待避線の考え方は、ワークロードを分離し、重要な処理が遅い処理に引きずられないようにする設計の重要性を示唆しています。
AWSのAuto Scaling やGoogle CloudのManaged Instance Groups でリソースを増やすだけでなく、リクエストの種類に応じてキューを分離したり、優先度を付けたりすることで、より応答性の高いシステムを目指せます。
| 鉄道の仕組み | SRE/クラウドの概念 | SREとしての活かし方 |
|---|---|---|
| 待避線 | 冗長構成、負荷分散 | ワークロードの分離、リソースの最適配分 |
| 優等列車の通過待ち | 優先度付きキューイング | 重要なリクエストを優先処理する仕組みの導入 |
| 臨時列車の増発 | スケールアウト | 負荷に応じた自動スケーリングの最適化 |
振り替え輸送から学べる「真の可用性」
万が一、事故や故障で電車が止まっても、他の路線を使った「振り替え輸送」で目的地に向かえます。これは皆さん分かりやすいでしょう。そう、システム障害時に備える「フォールバック」や「フェイルオーバー」そのものですね。
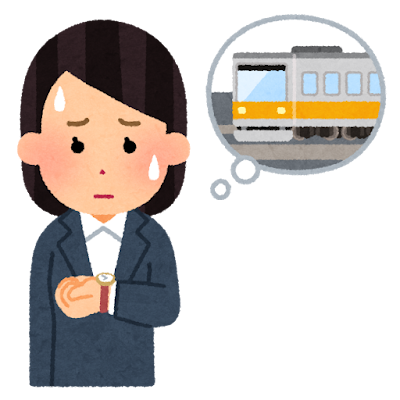
ここから学べること
「障害は起こるもの」と割り切り、いかに迅速に代替手段を提供してユーザーへの影響を最小限に抑えるか、という「回復力(レジリエンス)」の重要性です。
システムを落とさないこと(信頼性)も大事ですが、落ちた時にどうするか(可用性)を設計に組み込むことが、真のユーザー中心設計と言えます。
SREに活かせるポイント
AWSのMulti-AZ構成やAzureのAvailability Zonesを組んでいるから安心、で終わっていませんか?振り替え輸送が機能するには、日頃からの訓練と、どの代替経路が使えるかの周知が必要です。
SREとしては、カオスエンジニアリングなどを通じて定期的に障害訓練を行い、確実にフェイルオーバーすることを確認するべきです。また、一部の機能が停止しても、コアな機能は動き続けるような「縮退運転」の仕組みをアプリケーションレベルで検討することも、この学びの応用と言えるでしょう。
まとめ
毎日何気なく利用している鉄道ですが、その安定運行の裏側には、SREが日々向き合っている課題解決のヒントがたくさん詰まっていました!日常生活のさまざまなものに目を向けると、ふと今抱えている改善のヒントが見つかるかもしれません。



