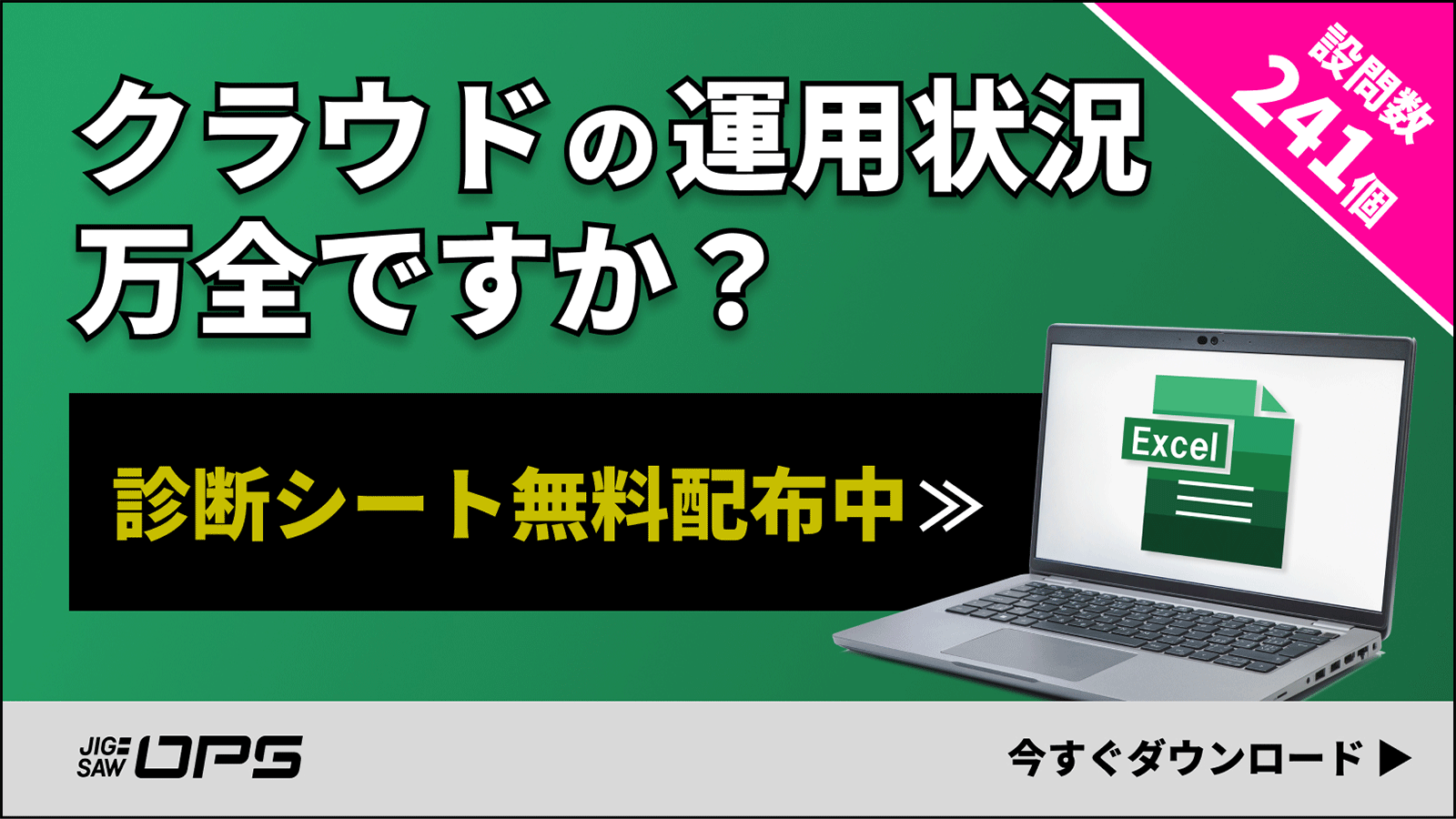Deepfakeの登場で「百聞は一見に如かず」が過去の言葉になった?
最近、業務の合間にこうしてブログを書く機会が増えている筆者。
文章をひねり出す工程の中で、表現の幅を広げようとことわざを調べていたところ、ふと「百聞は一見に如かず」という文字が目に留まりました。
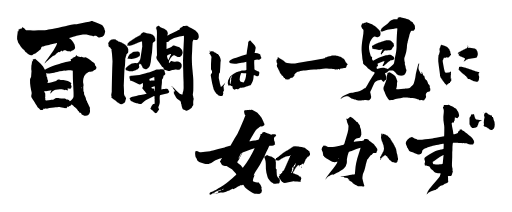
皆さんご存じの通り「人から何回も話を聞くよりも、一度自分で実際に自分の目で見る方が、確かでよく理解できる」という意味です。
しかし、AI技術が進化する現代において、必ずしも「百聞は一見に如かず」が正しいとは言えなくなってきていると思います。
本日は、その原因となっている、AIの「Deepfake(ディープフェイク)」という技術について語ってみたいと思います。
そもそもDeepfakeとは?
Deepfakeは、ディープラーニング(深層学習)とフェイク(偽物)を組み合わせた造語で、AIを使って非常に精巧な偽の映像や音声を作り出す技術を指します。
この技術の登場により、私たちが見ているものが本当に「真実」なのか、簡単には判断できない時代が訪れようとしています。Deepfakeは、AI、特にGAN(敵対的生成ネットワーク)と呼ばれる仕組みを利用して、本物と見分けがつかないほどのコンテンツを生成します。
例えば、ある人物の映像を学習させ、別の映像の中の人物の顔と入れ替えたり、存在しない人物に本物さながらの演説をさせたりすることが可能です。
元々は映画制作の効率化など、エンターテインメント分野での活用が期待されていました。しかし、その精巧さゆえに、悪意を持ったデマの拡散や詐欺などへの利用が懸念されています。
デジタル世界の「証拠」が揺らぐ時
Deepfake技術が突きつける最も大きな課題は、デジタルにおける「証拠」の信頼性です。
例えば、システム障害の原因を調査する際、監視カメラの映像が重要な手がかりになることがあります。しかし、もしその映像がDeepfakeによって巧妙に改ざんされていたらどうでしょうか。あるいは、経営者になりすました偽のビデオメッセージによって、不正なシステム変更が指示されるかもしれません。
このように、「見たもの」が必ずしも真実とは限らなくなる世界では、デジタルデータの完全性、つまり「そのデータが作成されてから誰にも改ざんされていないこと」をいかにして証明するかが、システム運用においても非常に重要なテーマになります。
クラウド大手はどう立ち向かう?
この新しい課題に対し、直接的に「Deepfakeを検知する」サービスをクラウド各社が提供しているわけではありません。
しかし、その根底にある「データの信頼性」を担保するための仕組みは、各社が提供するサービスの中に組み込まれています。これらは、デジタル世界の新しい「証拠」を守るための武器になると言えるでしょう。
以下に、主要なクラウドプラットフォームが提供するデータ完全性を保証するためのアプローチをいくつか紹介します。なお、ここで紹介する情報は各社の公式ドキュメントや技術ブログを基にしていますが、Deepfakeそのものに関する言及は一般的な情報源からのものです。
これらの技術は、データが「本物」であることを保証するための基盤となります。
新しい「真実」の守り方
Deepfakeのような技術は、私たちの「見る」という行為の価値を根本から変えてしまう可能性を秘めています。もはや、ただ見るだけでは不十分で、その情報が本物かどうかを「検証する」という視点が不可欠になります。
私たちエンジニアの役割も、これまでのシステムを安定稼働させることから一歩進んで、そこで扱われるデータが「信頼できるものであること」を保証する、「デジタルの真実を守る番人」へと進化していくのかもしれません。
これからは、目で見えるものだけでなく、その裏側にあるデータの来歴や完全性まで意識することが、より一層求められる時代になりそうです。